梅雨っていやですね…。
洗濯物は部屋干しになるし、湿気はひどいし、カビが大活躍するし、食中毒の心配も。
毎日毎日ぐずついた空模様なので、気分も下がりがち。
梅雨なんてなくなればいいのに、と毎年思うのですが、きちんと毎年やってきます。
年によっては短かったり長かったり、あまり雨が降らなかったりするけれど、それでもきちんと梅雨はやってくる…
はて、なぜでしょう。
目次
梅雨前線とは?梅雨前線の作られ方
 毎年5月末から7月にかけて、北海道と小笠原を除く日本各地では、約1か月ほど雨や曇りの日が続く梅雨の季節に入ります。
毎年5月末から7月にかけて、北海道と小笠原を除く日本各地では、約1か月ほど雨や曇りの日が続く梅雨の季節に入ります。
日本の5つ目の季節「雨季」とも呼ばれる梅雨です。
この時期、日本の北側には「オホーツク海気団(オホーツク海高気圧)」が、南側には「小笠原気団(太平洋高気圧)」が存在しています。
春から夏に季節が進むと、小笠原気団(太平洋高気圧)が次第に勢力を増し、日本の南の海上に停滞していた前線はゆっくりと北上してきます。
高気圧では下降気流が生じるので、地面に当たった気流は周辺へ吹き出す風となります。
オホーツク海高気圧から吹く冷たい北東風と、太平洋高気圧の縁を回るように吹く暖かく湿った南西風とが、本州付近でぶつかって停滞前線ができます。
どちらからの風も海上を通ってくるので、水蒸気を含むため雨が多くなる。
この停滞前線は、2つの高気圧の勢力のバランスが釣り合っているため、長期間にわたって停滞することになります。
この停滞前線が梅雨前線であり、日本列島は梅雨の季節に入ります。
なお、前線の活動や弱まると、一時的に晴れの日が続くことがあり、これを「梅雨の中休み」といいます。
梅雨の期間中、梅雨前線は北上・南下を繰り返しながら、全体として緩やかに北上していきます。
これは、夏に向けて、梅雨前線の南側にある太平洋高気圧の勢力が次第に強まってくるためです。
南の太平洋高気圧が北にあるオホーツク海高気圧を押し上げていくんですね。
特に梅雨の末期は、太平洋高気圧の縁(ふち・ヘリ)をまわるように、南から高音多湿な空気が次々と流れ込んで、積乱雲が発達し、集中豪雨による災害が発生することもあります。
そして夏が近づくにつれて、だんだん太平洋高気圧の勢力が強まり、梅雨前線はどんどん北に押し上げられて、
やがて天気図上から梅雨前線の姿が消え、太平洋高気圧にゆるやかに覆われるようになると、梅雨明けを迎え、本格的な夏が到来するのです。
なるほど~、季節の変わり目の気候条件が重なって、毎年この時期に梅雨と呼ばれる雨の季節が訪れるのね…
前線とは?前線についておさらいします
前線とは、暖かい空気(暖気)と冷たい空気(寒気)の境界が、地表と交わるところの事です。
前線には、寒冷前線・温暖前線・閉塞前線・停滞前線の4種類があります。
寒気の強い場合は寒冷前線、暖気の方が強い場合は温暖前線です。
寒気と暖気が拮抗している時は、停滞前線(長いあいだ同じ場所に留まる前線のこと)となり、梅雨前線(と秋雨前線)がまさにそれです。
梅雨の種類
梅雨には雨の降り方などによって2種類のタイプがあります。
強い雨や曇りといったぐずついた天気が続く、「陰性の梅雨」と、雨が激しく降ったかと思えば晴れ間がのぞくといったような、雨の降り方の変化が大きい「陽性の梅雨」の二つです。
陰性の梅雨は気温が低めになり、陽性の梅雨は気温が高めになります。
オホーツク海高気圧と太平洋高気圧との勢力が拮抗していることで、梅雨前線ができると説明しましたが、そのときにオホーツク海高気圧の影響が大きいと、陰性の梅雨になりやすく、一方で太平洋高気圧の影響が大きいと、陽性の梅雨になりやすくなります。
これは、太平洋高気圧からの風は温暖湿潤のため、積乱雲が発生しやすくなるためです。
一般的に、梅雨の前期には陰性の梅雨が多く、後期には陽性の梅雨が多くなります。
梅雨「つゆ」の語源は?
梅雨があるのは日本だけではありません。
東アジア特有の『雨の季節』です。
梅雨という言葉は中国から入ってきました。
中国では梅雨を「メイユー」と呼びます。
言葉自体は中国から渡ってきたとのことですが、その語源には諸説あります。
●「梅の実が熟す時期」に降る雨からきている説。
●長雨でカビが生えやすくなることからバイ菌のバイで「黴雨(ばいう)」と呼ばれていたが、語感が悪いため「梅雨」とした説。
そして、この梅雨を日本流に「つゆ」と呼ぶようになったことも諸説あります。
●「つゆ」はもともと水滴を意味する言葉で、「露(つゆ)」から変化した説。
●長雨の時期で、食べ物などが腐ったり痛んだりすることから「物が潰える(ついえる)」から「潰(つい)ゆ」となり、「つゆ」に転じたという説。
●梅の実が熟す頃という意味の「つはる」に由来する説。
●「梅の実が熟して潰れる頃」であることから、「潰ゆ(つゆ)」となった説。
諸説あり。
今ではどれが本当なのかはわからないのですが、梅雨「つゆ」と呼ぶようになった時期はハッキリしていて、江戸時代です。
この、梅雨と書いて「つゆ」と読む言葉。
日本特有の美しい響きだなと思います。
鬱陶しい長雨ですら、そこに風情を見出すのがまた、日本らしいなと思うのです。
梅雨(つゆ)と五月雨(さみだれ)の関係
 梅雨を「つゆ」と読むようになったのは江戸時代からですが、平安時代から江戸時代までは「五月雨(さみだれ)」と呼んでいました。
梅雨を「つゆ」と読むようになったのは江戸時代からですが、平安時代から江戸時代までは「五月雨(さみだれ)」と呼んでいました。
これは、当時は旧暦で季節を見ていたからなんですね。※旧暦について詳しくはこちら
旧暦の五月は、いまでいうと6月頃。
ちょうど、旧暦五月は雨の季節というわけです。
現代とは季節感が異なっていたため、昔からある言葉の季節がズレてしまうのは、情緒的に残念で仕方ありません。
現代では季節が1か月ほどズレてしまっていることで、「五月雨(さみだれ)」は、「初夏に入った明るい5月に時折降る雨」といった意味で使われており、そもそもの言葉の意味まで変わってきてしまっているんですよね。
もっと旧暦の存在感を増していけば、現代の味気ない毎日にももっと風情を感じられたり、昔ながらの日本らしさが出るのではないかと、個人的には思ってます。
梅雨の時期を乗り切るコツ
雨が続くこの季節は、外出も億劫になり、気分も下がりがちですが、雨音に耳を澄ましたり、雨の日特有のニオイを感じ取ったり、雨にぬれた紫陽花の鮮やかさに心を向けてみたり、感性を育てるのにはぴったりな時期とも言えます。
また、日本は農業国であり、この時期は農家最大の作業、田植えが始まる頃です。
田植えの様子や、緑鮮やかな田んぼにおたまじゃくし。
子どもの頃に味わったような懐かしさを覚えます。
そして、この後にやってくる灼熱の日本の夏を乗り切るために、水を沢山貯めておかなければなりません。
稲にとっても私たちにとっても、命といえる大切な雨。
自然の恵みに感謝です。
とはいえ、毎日の通勤通学が鬱陶しい…ですよねぇ
そこで、梅雨の季節を乗り切るためのコツを。
傘やレインブーツ、レインコートを新調することで気分を上げる作戦です。
身の回りのグッズが新しくなると、それを使う機会が待ち遠しいですよね。
毎日が雨のこの季節、お気に入りの雨グッズを用意することで、使うのが楽しくなりますよ☆
↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓
![]()
にほんブログ村





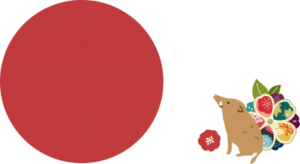




コメント