お正月明けの不健康な時に必ず耳にするこのニュース。
「1月7日は七草粥を食べる日です」
連日、食っちゃ寝、食っちゃ寝の正月休みでモタレタ胃に、消化のよい七草粥を食べて胃を休めてあげる。
時期的にもピッタリですね。
でも、じゃあなぜこの日に七草がゆを食べるのか、その由来が気になりませんか?
目次
なぜ一月七日に七草粥をたべるの?
古代中国では、
元旦の鶏(とり)に始まり、
二日に狗(いぬ)、
三日に猪(ぶた)、
四日に羊、
五日に牛、
六日に馬、
七日に人、
八日に穀物。
と、それぞれの豊凶や人の禍福(かふく:災いと幸せの意)・吉凶を、その日の天気で占う風習がありました。
つまり1月1日の元旦から1月8日までを、それぞれの日に動植物を割り当てて、順番にその日の天気でその年の運勢を占っていたんですね。
そして、それぞれその日に割り当てられた動植物を殺さない日とも決められていました。
そこで、七日は人の日として人を殺さない日とし、犯罪者を刑罰しない日と定めていたそうです。
人を大切に扱うことから転じて、7種の若菜を入れた粥を食べ、無病息災や立身出世を願う風習になったのです。
この風習が奈良時代に日本に伝わると、もともと日本にあった『年初めに芽吹いた若菜を摘んで食べる「若草摘み」』や、『1月15日に[こめ、あわ、ひえ、きび、ごま、小豆、みのごめ]という、7種類の穀物でおかゆを作る「七種がゆ」』などの、日本在来の風習と結びついていきました。
そして、一月七日の朝に、春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作り、ようやく芽吹いた春の七草の「気」をいただき、その一年の無病息災を願って食べるようになったといいます。
これは冬に不足しがちなビタミンCを補い、また祝い酒で弱った胃を休める為とも言われています。
こうして中国から伝わった風習が、日本の七草粥として成立していきましたが、当初は貴族社会だけの習わしで庶民には馴染みのないものでした。
それが庶民に広がるようになったきっかけは、江戸時代に五節句のひとつに制定されてからということです。
なぜ1月7日に七草粥なのか?それは、中国の古い占いで一月七日 が『人を大切にする日』と割り当てられており、そこから派生した風習だったのですね。
※注:七草粥の具は地方によって変わることがあります
なぜ1月7日は人日(じんじつ)の節句なの?七草粥との関係は?
節句とは、日本の暦における伝統的な年中行事を行う季節の節目(ふしめ)となる日のことで、1年に五つあり、五節句もといいます。
3月3日、5月5日、7月7日など、同じ数字が並ぶ五節句の中の唯一の例外は、この1月7日の『人日(じんじつ)の節句』です。
この日は、1月1日から行われるさまざまな新年行事がひと段落ついたころで、七草粥を食べる日としてよく知られています。
前述したように、古代中国の占いの書には、正月1日には鶏、2日に狗、3日に猪、4日に羊、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀を占って、その日が晴天ならば吉、雨天ならば凶の兆しである、とされていました。
1月7日の「人の日」には、邪気を祓うために七草の入った粥をたべ、一年の無事を祈る。
七草粥に入れるのはいわゆる春の七草、初春の野から摘んできた野草の生命力を食して、邪気を祓うということを願ったのです。
そんな中国の古い慣習が日本に渡り、一月七日は人の日=人日という事で、更に江戸時代に五節句の一つと制定されてからは、『人日の節句』と呼ばれるようになりました。
七草粥の植物の種類・七草がゆの効用効能は?
●セリ:香り豊かな、水辺に生える山菜で、食欲増進によい。鉄分が多く含まれており、増血作用が期待できます。
●ナズナ:いわゆるぺんぺん草。当時一般的な食材として取り入れられていた。 熱を下げ、尿の出をよくするなどの作用がある。
●ゴギョウ:別名・母子草。かぜの予防や解熱に効くとされる。
●ハコベラ:目に良いとされるビタミンAが豊富。腹痛の薬にも。タンパク質が比較的多く含まれ、ミネラルそのほかの栄養に富んでいるため、民間では古くから薬草として親しまれていた。
●ホトケノザ:別名タビラコといい、食物繊維を豊富に含んでいる。
●スズナ:蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。消化を促進する。
●スズシロ:大根のこと。消化を助け、かぜの予防にもなる。
いずれもみずみずしい緑の草ですから、ビタミンがたっぷり含まれています。
緑が不足しがちなお正月、滋養豊かな七草で疲れた胃を休めるのは、暴飲暴食の続いたこの時期にとてもいいですね。
今年は七草粥の伝統を取り入れて、今年一年が良い年であるようにと家族みんなで願掛けしてみては? ※注:七草粥の具は地方によって変わることがあります。
七草がゆの作り方
七草粥はこれまでお伝えした通り、人日の節句の朝に、7種の野草あるいは野菜が入った粥を食べる風習のことです。
では、その七草粥とはどのように作るのでしょうか。
七草粥の作り方です。
【材料】は 4 人分です。
米・・・・・・・・・・・・・1 カップ
水・・・・・・・・・・・・・5~6 カップ
春の七草・・・・・・・・・・適量
塩・・・・・・・・・・・・・適量
【作り方】
① 米を洗い、水を加えて火にかける。煮立ったら弱火にして、40~50 分煮る。
② 大根(スズシロ)と蕪(スズナ)の白い部分は、イチョウ切りにし、米と一緒に煮る。
③ 七草の葉は、塩少々を入れたお湯でさっと茹でてアクを抜き、水にさらす。
④ 七草を軽く絞って水気を取り、みじん切りにする。
⑤ 米がやわらかく炊けたら七草と塩をいれ、軽く混ぜて火を止める。
⑥ 適当な容器に入れ出来上がりです。
塩だけだと青臭さが気になる、という方はお好みでお味噌やお醤油、梅干しなどで味付けをして工夫しましょう。
我が家流の七草粥として、家の伝統にしてもいいですね!(^^)!
※七草粥の具は地方によって変わることがあります
人日の節句を英語で説明してみよう
東京オリンピックも近づいており、日本に訪れる外国人観光客は過去最高を記録し、さらに右肩上がりとのことです。
日本政府観光局(JNTO)によると、2017年1月~12月の年間訪日外客数は、28,691,073人でした。
増え続ける外国人といつどこで知り合うかわかりません。
そんな時にコミュニケーションで困らないよう、日本の文化を英語で伝えられるといいですよね。
という訳で、『人日の節句』を英語で説明するとどうなるのか。
・人日(じんじつ)とは、五節句の一つ。
Jinjitsu is one of the 5 sekku that mark changes in the seasons.
・七草(ななくさ)は、人日の節句(1月7日)の朝に、7種の野菜が入った羮を食べる風習のこと。
The seven herbs of spring (Nanakusa) is a custom of eating hot soup containing seven vegetables on the morning of Jinjitsu no Sekku, the so-called Person-Day Festival (January 7).
・江戸幕府の公式行事となり、征夷大将軍以下全ての武士が七種粥を食べて人日の節句を祝った。
It subsequently became the official event of the Edo bakufu (Japanese feudal government headed by a shogun) to have the dish on January 7, when all the warriors including the great general celebrated the day eating nanakusa rice porridge.
出典:weblio英語例文より
七草囃子(ななくさばやし)とは
七草を刻むときに、大きな声で「七草囃子」を歌いながら刻む民間風習があります。
七草囃子『七草なずな、唐土の鳥が、日本の土地に、渡らぬ(届かぬ)先に、トントンバタリ、トンバタリ~』 と唄い、農作物を荒らしてしまう鳥たちが、日本入ってくるのを避けようというおまじないです。
農村部で行われている「鳥追い」という習わしと結びつき、豊作への願が表されています。
また、こうした七草囃子を唱えながら、大きな音を立てて七草を刻むと、七草がゆの効果も高まると考えられていたので、包丁でまな板を叩くだけではなく、おたまやすりこぎなどの調理器具を叩きながら、にぎやかに刻む風習もあります。
七日正月に七草粥を食することは、元旦から続く正月行事が終わる直会(なおらい)※の日であり、
餅に疲れたお腹を休めるための理にかなった行事といえるのです。
ニッポンの伝統行事って、その根拠を調べてみるときちんと説得力があるんですね。
※直会(なおらい)とは…祭事が終わってから神酒(みき)・供物を下げていただく宴会。その下げた供物。
↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓
![]()
にほんブログ村



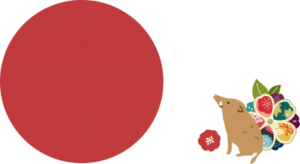




コメント