11月の休日。
晩秋のカラッとした清々しい天候の中で見かける着物姿の子供たちと幸せそうなそのご家族たち。
でも七五三ってなんで7歳5歳3歳なの?
七五三と言えば千歳飴…、てなぜ???
知らないことだらけですね。
あなたは七五三についてどれだけご存知ですか?
目次
七五三とは
七五三とは、3歳・5歳・7歳と成長の節目に近くの氏神様に参拝して無事成長したことを感謝し、これからの将来の幸福と長寿をお祈りする行事です。
中国では奇数は陽数、偶数は陰数と言われ、奇数は縁起のいい数字とされます。
詳しくはこちらをご覧ください。
それを受け、日本でも奇数を喜びの吉数と尊び、子供たちの成長の節目としてきました。
医療が十分に発達せず子供の死亡率の高い時代には、子供の成長や健康を願うため、お七夜やお宮参りなどの風習が生まれました。
七五三もそういった習慣の一つで公家や武家が発祥です。
七五三の由来
平安時代の頃から【髪置(かみおき)】【袴着(はかまぎ)】【帯解(おびとき)】の儀式がありました。詳しくは後述。
時代によって男女の別は異なり、年齢も3歳・5歳・7歳に限らず、11月15日の決まりもありませんでした。
3歳・5歳・7歳を祝う風習は江戸時代から生まれました。
三代将軍家光が、後(のち)の五代将軍綱吉(幼名:徳松)が病弱であることを心配し、無事成長を祈るために袴着の儀式を行ったのが11月15日でした。
3・5・7という数字は、祝い事に用いる数を奇数(陽の数)としたた中国の思想に基づき 、1・3・5・7・9の中の3つを取ったものです。
その後、明治時代になり「七五三」という名称が成立し七五三の風習が盛んになりました。
髪置(かみおき)・袴着(はかまぎ)・帯解(おびとき)の儀とは?
【髪置きの儀】
それまで剃っていた髪の毛を長く伸ばして唐子まげを結う男女の儀式。
平安時代は、男女ともに三歳までは坊主頭で、三歳の春から髪をのばし始めます。 碁盤の上に子供をのせ、決められた着衣を着て儀式を行います。 子どもが将来白髪頭になるまで長生きするようにと言う祈りを込めて、白髪に見立てた綿帽子を子どもの頭に載せる行事が髪置(かみおき)の儀です。 女子はその後、余程の事でもない限り生涯髪を切りませんでした。
【袴着の儀】
幼児から少年・少女へと成長することを祝い、初めて袴を着ける儀式。皇室では愛子さまも「着袴の儀」をされているように古くは女の子にも行われていたが、現在では男の子の祝いとなっている。
平安時代は、男女ともに初めて袴をつける儀式です。
「袴」という大人が公の場で身につける衣服を着用すると言うことで、男として社会の一員となると言う意味を持つものなのでしょう。なお、この際に子どもに冠を着けさせて碁盤の上に載せ、腰結いの役の人が袴をつけました。
そして四方の神を拝させたと言います。
碁盤は「勝負の場」の象徴として用いたものらしく、この子が大きくなって出会うであろう人生での様々な「勝負の場」で四方を制するという意味を持ったものとか。
江戸時代以降は、男子の正装である袴と小袖をつけて扇を持つ男子のみの風習となりました 。
【帯解の儀】
女の子の祝い。「紐落とし」とも言う。これまで着けていた着物の紐を外し、本式の帯を絞め儀式。
鎌倉時代、子供の着物は紐で着付けていましたが、この紐を取りその代わりに大人と同じに帯を締める儀式が始まりました。女子はこのとき初めて被衣(かづき)をかぶる儀式もしました。いわゆる大人の女性の仲間入りをする日です。帯を締めるのに「帯解?」という気もしますが、ここで解くのは「着け帯び」のことです。なお、帯は「魂をその内にしっかりととどめおく」ものだそうで、帯を締めることによって、身を持ち崩すことのないようにと言う願いを込めるものとか。
七五三の儀式
それぞれの歳の子どもは晴れ着姿でお参りに行きます。
神社では参拝するだけでもいいですし、お祓(はら)いを受け祝詞(のりと)をあげてもらうこともできます。
その際はお礼を包みます。
包み方などのマナーはこちら
数え年で行なうのがしきたりですが、最近では満年齢で行うこともあります。
現在では全国で盛んに行われていますが、元来は関東圏における地方風俗でした。
千葉県や茨城県地方では、今でも七五三のお祝いをホテルなどで結婚披露宴並に豪華に開催する場合もあります。
武家社会の頃から行われるようになったという儀式は上記で説明した通り。
【髪置(かみおき)】【袴着(はかまぎ)】【帯解(おびとき)】の儀。これらをひとまとめにしたのが七五三です。
誕生から年月を経たわが子の姿を神様に見ていただき、さらに健やかな成長を祈るという、大切な行事なのです。
七五三はなぜ11月15日に行われるの?
七五三が11月15日に行なわれるようになったのは江戸時代の末期です。
旧暦の15日は、かつては二十八宿(にじゅうはっしゅく※1)の鬼宿日(鬼が出歩かない日)に当たり、何事をするにも吉であるとされました。
また、旧暦の11月は収獲を終えてその実りを神に感謝する月であり、その月の満月の日である15日に氏神への収穫の感謝を兼ねて子供の成長を感謝し加護を祈るようになったと言われます。
明治改暦以降は新暦の11月15日に行われるようになりました。
全国的に七五三の行事が広まったのもこの時代。
現在では11月15日にこだわらずに、11月中のいずれかの土日・祝日に行なうことも多くなっています。
北海道等、寒冷地では11月15日前後の時期は寒くなっていることから、1ヶ月早めて10月15日に行なう場合が多いです。
※1 二十八宿…月の運行による日の数え方
七五三と千歳飴の関係
江戸時代(1688~1704年頃)浅草の飴売り七兵衛が紅白の棒状の飴を「千年飴」「寿命糖」と名付け、長い袋に入れて売り歩いたことが始まりとされます。
また別の説では同じ江戸時代、浅草で平野甚右衛門という飴屋が売り出したものがその始めとも言われます。
最初から現在のような縁起物として売り出したわけではなく、【七五三の土産に】と言う現代風に言えば販売効果を狙って、鶴亀・松竹梅をあしらった図柄の袋に入れたり、「千歳」などのめでたい言葉を付けたりしたものです。
ところで「鶴は千年 、 亀は万年」というように、鶴と亀は長生きのシンボルです。
人生50年とした昔の人から見ると、驚くほど長生きの生き物だったわけですね。
千歳飴は鶴・亀などの長寿や吉向を表す絵柄の袋に入れられ、子どもの末長い健康と幸せを願った縁起物なのです。
七五三を外国人に英語で説明しよう!
東京オリンピックも近づいており、日本に訪れる外国人観光客は過去最高を記録し、さらに右肩上がりとのことです。
日本政府観光局(JNTO)によると、2017年1月~12月の年間訪日外客数は、28,691,073人でした。
増え続ける外国人といつどこで知り合うかわかりません。
そんな時にコミュニケーションで困らないよう、日本の文化を英語で伝えられるといいですよね。
まとめ
七五三の由来でした。
小さな男の子があの勇ましい着物姿を見せてくれると、とたんに逞しく見えますよね。
昔の武士の子供は本当に大人びていました。
大人への通過儀礼が早い時期にあったことが、自覚を促し心身共に成長を早めたのかもしれません。
あとは単純に今よりももっと短命だったので、早熟にならざるを得ないというところだったのでしょうか。
今は何とも子どもっぽい大人(childish)が多いので、少し見習いたいものですね。
↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです
![]()
にほんブログ村



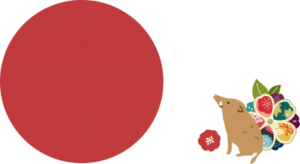




コメント