5月5日は端午の節句。
この日は五節句の一つで、男子の健やかな成長を祝い、祈る日とされています。
この日、男の子のいる家庭では、こいのぼりを飾ったり、兜(かぶと)をかざったり、柏餅(かしわもち)を食べたり、菖蒲湯(しょうぶゆ)に浸かったりしますね。
さて、なぜ端午の節句が子どもの日になったのか?
なぜ兜を飾ったり、
柏餅を食べたりするのか?
あなたはご存知ですか?
目次
端午の節句の意味や由来は?なぜ五月五日になったの?
端午の節句の起源は、古代中国にさかのぼります。
端午の「端(たん)」は、はじ・最初の意味で、「午(ご)」は、うま、つまり端午とは、最初の午の日という意味で、当初は五月に限ったものではありませんでした。
そのうちに、「午(ご)」は五に音が通じるとして、五の字が重なる日に特別の意義を認めて、古代中国の時代に五月五日を『端午』というようになりました。
古来中国では、もともと五月は物忌み(ものいみ:不吉であるとして神事を忌み避けること)の月とされ、厄払いの行事が盛んに行われていました。
中国では、奇数を陽数として好み、偶数を陰数として嫌う思想が昔からあり、陽(奇数)が重なる(極まる)と陰に転じるとして不吉とされることから、それを避けるための魔除けの行事も行われていました。
5月5日は陽(奇数)が重なっており、陽の極まる日。
そこで、身の穢れや不浄を祓う行事がこの日に行われたのです。
五月五日は薬草を摘み、ヨモギで作った人形や虎を門に掛け、邪気を祓うとされる菖蒲は刻んでお酒に入れて飲んだり、粽(ちまき)を食べるという行事が行われました。
これらは邪気を払い、病気や災いを避けると考えられていたということです。
こうした中国の考えや風習は、そのまま日本に紹介されましたが、元々日本では、端午の節句は女の子のお祭りでした。
日本には田植えを始めるシーズンである5月、早乙女(さおとめ)と呼ばれる若い女性たちが、田の神様に豊穣(ほうじょう)を祈るため巫女(みこ)となり、菖蒲やヨモギで葺(ふ)いた仮小屋や神社などにこもって、身の穢れを祓う習慣がありました。
この儀式の事を「五月忌(さつきい)み」といいます。
当時の日本は稲作中心だったため、稲の豊穣は何よりも大切なことで、日本ではこの日、田の神様に対する女性による厄祓いの日だったというわけです。
この元々あった日本古来の風習が、中国から入ってきた厄払い行事と結びつき、日本でも端午の節句が宮中行事として行われるようになり、中国と同様、日本でも菖蒲の薬効と香りは穢れを祓うとされ、厄除けとして使われるようになりました。
軒に菖蒲を吊るしたり、菖蒲の葉を浮かべたお風呂(菖蒲湯)に入ったりするなど、現在の風習にも通じる習慣が定着しました。
これが男の子のお祭りになるのは、武士が台頭してくる時代になってからです。
それまでは宮中での厄払い行事だったものが、鎌倉の武家社会へと広がります。
武士の間では、尚武(しょうぶ・武道を大切なものと考えること)の気風が強く、「菖蒲」と「尚武」をかけて、端午の節句を『尚武の節句』として盛んに祝うようになりました。
江戸時代に入ると幕府は五月五日を五節句のひとつとして重要な日と定め、大名や旗本は式服(儀式に着用する正式の服。礼服)で江戸城に参じ、将軍にお祝を奉じるようになりました。
また、将軍に男の子が生まれると、門前に馬印(うましるし・戦場で敵味方の識別や武将自らの存在を誇示するために用いた目印)や、幟(のぼり)を立てて祝いました。
幕府が節句のひとつとして制定し奨励したことで、これらの風習が武士だけではなく、庶民の間にも広まっていきます。
武家の幟(のぼり)に対し、庶民は鯉のぼりを飾り、また紙で作った兜(かぶと)や人形を飾り、これが武者人形などに発展していきました。
このようにして端午の節句は、上巳(じょうし)を女子の節句にするのに対して、男子の節句となりました。
その後、昭和の時代に五月五日が子供の日と決められてからは、国民の祝日となって今に至ります。
こいのぼりの由来
中国の故事に由来します。
黄河の急流にある「竜門」と呼ばれる滝を、多くの魚が登ろうと試みたが、失敗。
すると鯉のみが登り切り、竜になることができた、という伝説にちなみ、鯉の滝登りが立身出世の象徴となりました。
また子供が生まれた家では、「この家の子供をお守りください」と、天の神様に向かって目印にみたてた、という話もあります。
栄達するための難関を「登竜門」と呼ぶのも、この故事にもとづく言葉です。
日本では江戸中期ごろより、男児誕生の際には、家の敷地の一番高い場所にこいのぼりを掲げ、天の神様にお知らせをし、神のご加護を祈る事が習わしとされてきました。
逆風に向かって風を含み、大きく勇壮に泳ぐ鯉のぼりは、日本の五月の空を鮮やか彩る象徴にもなっていますね。
一年の中で、最も過ごしやすく気候のよい五月の青い空に、優雅に泳ぐ鯉のぼりを見ると、晴れ晴れしい気分になります。
端午の節句に柏餅や粽(ちまき)を食べる意味
端午の節句に柏餅(かしわもち)を食べるという習慣は、江戸時代初期から行われるようになりました。
粽(ちまき)は中国の風習が、そのまま日本に伝わったといいます。
柏は、枯れ葉になっても散ることなく、新しい芽が出るまで枝に留まり、新芽の成長を見守っています。
このことから柏の葉は、家系が代々栄える事の象徴となりました。
子孫繁栄を象徴するものとして縁起がよいとされています。
粽は、中国戦国時代の忠臣であり詩人でもあった屈原(くつげん)が、5月5日に川に身を投じ手死んだことを人々が悲しみ、毎年命日には竹の筒に米を入れたもので供養したことが起源となっています。
ある年、供養のときに屈原の霊が現れ、「米を龍に取られてしまうので、竹筒ではなく龍が嫌がる茅(ちがや)で包み、糸で結んでほしい」と言ったことから、今の形になったと言われています。
「粽」の名称は、以前は茅の葉などで巻いていたことから、「茅巻(ちまき)」というようになったことに由来します。
粽(ちまき)の作り方
もち米を扱うなんて難しそう…。
な~んて思っていたけれど、炊くのではなく、炒めてから蒸すので意外に簡単です♪
【材料】は 4 人分です。
もち米・・・・・・・・・・・・・3カップ
豚もも肉(ブロック)・・・・・・・150g
ゆでたけのこ・・・・・・・・・・150g
にんじん・・・・・・・・・・・・1/2本
干ししいたけ・・・・・・・・・・4枚
サラダ油・・・・・・・・・・・・大さじ4
(A)
しょう油・・・・・・・・・・・・大さじ4
水 ・・・・・・・・・・・・2カップ
【作り方】
① もち米は洗って、7~8時間水につけ、ざるにあげて水気をきる。
② 豚肉、たけのこ、にんじんは各々5mm角に切る。干ししいたけは水でもどし、5mm角に切る。
③ 鍋にサラダ油大さじ1を熱して豚肉を炒め、色が変わったら野菜を入れて炒める。(A)を加え、煮汁が半量になるまで煮詰める。
④ 別の鍋にサラダ油大さじ3を熱し、①を透き通るまで炒め、③を入れて混ぜ、8等分する。
⑤ 竹の皮に④をのせ、三角に包み、たこ糸でしば
⑥ 湯気の立った蒸し器で40~50分蒸す。
※竹の皮の代わりにアルミホイル(10cm角)で包んで、30分ゆでても手軽においしくできます。
粽(ちまき)は冷めても美味しいのでお弁当に入れてあげてもいいですね
端午の節句子どもの日を英語で説明しよう!
東京オリンピックも近づいており、日本に訪れる外国人観光客は過去最高を記録し、右肩上がりとのことです。
日本政府観光局(JNTO)によると、2017年1月~12月の年間訪日外客数は、28,691,073人でした。
増え続ける外国人とのコミュニケーションに困らないよう、日本の文化を英語で伝えられるといいですよね。
という訳で、端午の節句・子供の日を英語で説明するとどうなるのか。
・5月5日は子供の日です。
May 5 is Children’s Day.
・兜と鎧をつけた子供の日の人形
in Japan, a doll for Boy’s Day that has armour and a helmet.
・こいのぼり
a carp streamer
・鯉幟を立て子供の日を祝う
celebrate Children’s Day by putting up carp streamers.
出典:weblioより
今では、子どもの日はGWの連休最終日ですね。大型連休の最終日とあって、大人は少々憂鬱な日ですが(笑)、子供たちはいろんな行事もあって楽しい一日です。
子どもたちの健やかな成長を祈り、また、伝統行事の意味を知り、後世へ継承していって欲しいですね。
↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓
![]()
にほんブログ村



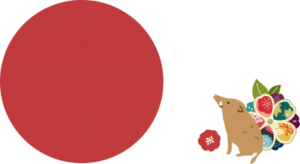




コメント